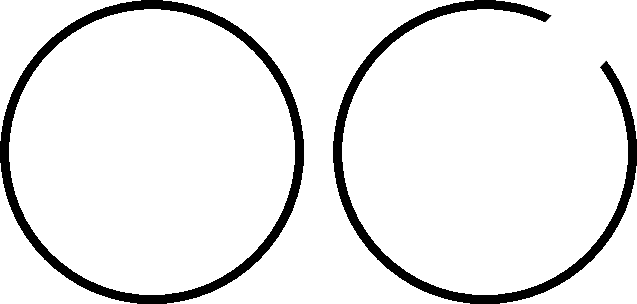人事評価と人材育成
「人事評価は人材育成のために」
人事評価制度を作る際によくテーマとして挙がります。
読者企業では具体的にどのような取り組みを行っているでしょうか?
よくあるのは、「フィードバック面談を通じて人材育成に繋げる」というものですが、評価者訓練が不十分なことが多く、スローガンで終わっている企業が多いかと存じます。
最低限としてはそれで良いかとも思いますが、本気で人事評価を人材育成に繋げたいなら、もっと工夫をする必要があります。取り組みの一例をご紹介します。
■評価で大切なのは「4点」の基準づくり
まずは人事評価について少しお話します。
多くの場合、能力評価(行動評価、コンピテンシー評価 等)は5段階で評価します。国家公務員の評価基準を参考にすると、
5点:非常に優秀
4点:優秀
3点:良好(←ここが標準)
2点:やや不十分
1点:不十分
といった評価評語になります。
ちなみに、国家公務員は最上位に「卓越して優秀」という基準があり、6段階評価となっていますが、一般的な企業では5段階評価が多数です。
評価標語の検討に当たり、評価を機能させるためのコツは下記の通りです。
① 通常、5点と1点はあまり使いません。特筆すべき何かがあった場合のみ使用します。意外と評価者に周知されていないことが多いようですので、評価者研修等を通じて周知する必要があります。
② よって、よく使用するのは4点・3点・2点の3段階です。平易な言葉で言い換えると、「良い」「普通」「悪い」の3段階をつける訳です。
③ 評価評語を考えるにあたって、2点(悪い)の基準は評価事実が明確であることが多いものです。心理学に「未完の円」理論というものがあります。
左と右と、どちらが気になりますか?という、あれです。
多くの人は右と答えます。理由は、人間は本能的に欠けている部分に目が行きやすい(不完全な部分が気になる)動物だからです。詳しく知りたい方は、「ツァイガルニク効果」なども調べてみてください。
よって、「未達」「ミス」「低品質」などは目につきやすく、記憶にも残りやすく、評価事実としても捉えやすい事象となります。評価評語としてはつけやすく、被評価者も認識している場合が多く、評価のブレは大きくありません。
④ 問題は、4点の基準です。簡単につける評価者もいれば、なかなかつけない評価者もいます。評価者により平均点が大きくぶれる原因は、4点の使い方評価者により様々であるためです。逆に言うと、4点の基準さえはっきりしてしまえば、4点に満たないものが全て3点です。3点の基準が明確である必要はないとも言えます。
結論、評価制度では4点の基準が肝と言え、ここの基準づくり(浸透)に注力すべきです。
■人材育成でも大切な「4点」の基準
一般的に、4点を取れる項目が増えれば、昇格が近くなります。言い換えると、本人が成長している証だとも言えます。4点の基準を明確にすることがが、人材育成にとって非常に重要なことと言い換えられます。
ただしこの4点の基準は、等級により、職種により、もっと言えば個人の職務により異なります。故に、会社として統一の基準づくりが難しく、人事評価と人材育成がつながらない要因の一つと言えます。
筆者がお勧めしている方法は、人事評価に際し、「3点以外をつける場合は、その理由を記載する」ことです。これにより、4点の基準=育成の基準が言語化されます。また、評価者と被評価者の間で、「どうやれば4点がつくのか=成長するのか」が話し合われることになり、フィードバック面談が人材育成のツールとしてより機能しやすくなります。
進める上での問題点は、評価に手間がかかること、コメント不要となる「3点」が増えがちであること(中心化傾向)などがありますが、本気で人事評価と人材育成をつなげたいなら、時間をかけ、評価者教育を行い、クリアすべき問題だと言えるでしょう。
もちろん、これだけやっておけば人材育成が進む訳ではありません。そもそもの人材育成のセオリーや、評価者の言語化能力の強化を、Off-JT等を通じて会社としてバックアップする必要もあります。
よって、人事評価を人材育成につなげるための第一歩と考えていただき、まずはスタートさせていただければと思います。
人材育成との理論的なつながりは、また別の機会でお話したいと思います。